
オール・シングス・ナイス
目次
プロローグ
第一章 史上最大の作戦
第二章 美女と野獣
第三章 ショウほど素敵な商売はない
第四章 雨に唄えば
プロローグ
と、正志は言った。
僕の頭の中に、水平線の彼方に小さくなっていく、白い大きな船の姿が浮かぶ。見送る僕は冷たい水の中、必死に手を振り、助けてくれと大声で叫ぶのだが、無情な船はどんどん、どんどん、どんどん遠ざかっていく。僕を広い大洋のどことも知れない一点に残して。やがて、力尽きた口中に塩辛い水が侵入してくる。
僕は恐ろしく心細くなって、弱々しく抗議の声をあげた。「それはひどいよ。レールからはずれるって言った人はいるけど」
「同じことさ」
正志はきっぱりと断定した。「シベリア横断鉄道からはずれてみろよ。シベリアの夜は氷点下四十度だぞ」
「凍死するね」
「地面が凍りついてて墓も掘れない」
シベリアの荒野にさらされた、哀れな自分の骨を想像した。
「そうなりたいか」
正志の声には死刑宣告を下す裁判官の冷厳がある。
「もちろん、いやだよ」
野ざらしなんて。
「ならば、この会社、絶対に受かるんだ。この仕事は俺のものだ、誰にも渡さない。その意気込みでいけ」
正志は体育会系だ。僕はいつも、鬼監督に呼び出された新入部員のように、首うなだれてやつの説教を聞くはめになる。
「今の世の中、非正規は人間じゃない。ひとなみに暮らしたかったら何がなんでも正社員の地位を手に入れろ。邪魔な奴は蹴り飛ばせ」
「そんな無茶な……」
「無茶じゃない。おっとり構えて暮らせるほど、世の中甘くないんだ。お前はずっと世間をなめてきた。ここらで死にもの狂いにならないと、末は……」
「わかってるよ」世間の塩辛さは。
「しっかりやってこい」
「でも、どうだろ。ハローワークでも、採用枠は一人なのに、もう五十人以上が応募してるって言ってたし、競争きつそう」
「じれったいなあ、お前は。それよこせ」
正志は僕から履歴書と職務経歴書の入った封筒をひったくると、家の奥に向かった。築四十数年。昭和に建てられた家は、ちまちました小部屋が無駄に多く、今時、和室の四畳半がある。薄暗くかび臭いその部屋には、祖父母の位牌を収めた、趣味の悪い金ぴかの仏壇が置いてある。正志は封筒を仏壇にお供えして、ちん、とリンを鳴らした。
「おじいちゃん、おばあちゃん。登はこれから、大事な就職試験に臨みます。登がめでたく合格して、正社員になれるように、どうぞ見守ってやって下さい」
再び、ちん、とリンを鳴らし、ぱんぱんとかしわ手を打って、手を合わせた。
「ほら、お前もちゃんとお願いしろ。本人なんだから」
言われてしょうがなしに、僕は手を合わせ、「よろしくお願いします」とつぶやいて頭を下げた。この際、わらでも神仏でもご先祖様でも、すがりたい気分には違いなかった。
「これで大丈夫。お前きっと受かるよ。そしたらみんなで祝杯あげようぜ」
正志は封筒を僕に返して、にこにこした。
「だといいけど……」
僕はあやふやに言った。
「なんだよ」
体育会系のこの言葉には、文句あるのか、という脅迫が潜んでいる。
「かしわ手って、神様にするものじゃなかったっけ。仏様にするのは変だよ」
僕は純粋培養の文系だ。この手の無用の知識だけは豊富に持ち合わせている。
「いいんだよ、そんなこと。孫なんだから、ゆるしてくれるよ」
体育会系は身内の寛容には絶対の自信をもっている。従兄というのは、DNAの八分の一を共有している計算になるそうだが、僕はかねがね、正志と僕との共有率はゼロに近いんじゃないかと疑っている。言葉にしたことはない。家庭争議の基になる。
「祝杯ってのは本気だからな。『うまい屋』の特製スモークサーモン、おごってやるよ」
「本当?」
「お祝いだからな」
悪い奴じゃないんだ。
「聡美も呼ぼうぜ」
前言撤回。
妹の聡美は、短大を出た後、市役所に勤めてる。子供の頃から僕とは気が合わない。第一、妹のくせに兄貴を呼び捨てにするのが気に食わない。「登、年を考えなさいよ。ボヘミアンなんて、社会に順応できない落ちこぼれよ」「適性なんてどうでもいいの。真面目に働いて、社会に貢献できる人材が、今、求められているのよ」
常に正論を吐く奴で、長く一緒にいると、某新聞を一週間分、一気読みしたような気になる。
履歴書を郵送して二週間後、書類審査合格、面接の知らせが来た。仏壇の奥のご先祖様に報告しながら、僕は、かしわ手のバチが当たったんじゃないかと真剣に疑っている。
第一章 史上最大の作戦
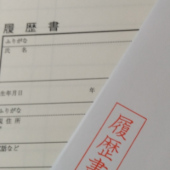
「お名前をお呼びするまで、このお部屋で、お待ちくださいませ」
案内の女子社員がドアを開けると、LEDで明るく照らされた、清潔で殺風景、味も素っ気も面白味もない部屋だ。普段は会議室にでも使われているのだろう。細長いテーブルが教室みたいに並んでいる。そこに二十人ぐらいの人間が男女とりまぜてすわって、首だけこっちに向けて無表情に僕を眺めていた。
「お好きなところにおかけください。テーブルの上に弊社の会社案内がございます。ご自由にお持ちください。では、申し訳ありませんが、しばらくこのままお待ちください」
女子社員が、僕を残して出ていくと、こっちを向いていた頭はまた一斉に正面を向いた。数えてみると、十四人。僕も含めて十五人。男が十人、女が五人だった。皆、黒っぽいスーツを着て、髪をぴったりとなでつけている。僕もそうしてきた。実はこの髪については、涙ぐましい苦心と工夫があったのだ。
昨夜、聡美が家にやってきた。普段は役所の近くの単身者向けの寮に入っていて、めったに顔を見せないのに。
「聞いたわよ、登。明日、面接なんだってね。身だしなみ、ちゃんとするのよ。面接官はそういうところを見るんだから。清潔感があって、目立たないようにするのよ」
「目立たなきゃ選んでもらえないだろ」
「オーディションじゃないの。スーツは? どれ着ていくつもり?」
選ぶほど持ってない。大学に入学した時に買った一着だけだ。卒業式も、正志の結婚式も、祖母の葬式の時もその濃紺の上下で通した。このところ運動不足で、二の腕のあたりがちょっときつい。でも、他にないから、それで行く。
僕がそう言うと、聡美はフンと、馬鹿にしたように鼻を鳴らした。
「それしかないなら、仕方ないか。シャツは?」
「クリーニングから戻ってきたままのがある。おばあちゃんの初七日の時、ケチャップをつけちゃって、染み抜きしてもらったんだ」
「ほんと、ドジよね」
その後、ネクタイは、かばんは、靴は、ハンカチはと矢継ぎ早の点検が続き、僕はダメ出しを食らってネクタイにアイロンをかけ、かばんの埃を払って金具を磨き、靴にブラシをかけるはめになった。へとへとになって、
「これでいいだろ」
だが、聡美は僕の頭に、ぴたり、と人差し指を突き付けた。
「その頭。床屋へ行ったのはいつ?」
ここ数年、御無沙汰してるとも言えず適当にごまかした。
「えっと、一年ぐらい前だと思う」
「一年前!」
聡美は、うちの冷蔵庫で六か月前に賞味期限の切れた冷凍ギョーザを発見した時のような叫びを発した。僕が「もったいない」精神を発揮して、そのギョーザを食べてしまった時は、もっと騒いだ。別に、どうということはなかった。特にうまいとも思わなかったけど、僕は美食家ではない。倹約家である。腹の痛みより、懐の寒さの方が身にこたえる。
何の話だっけ?
そうだ、散髪の話だ。
「その雀の巣みたいな頭を見たら、どこも採用してくれないわよ」
「雀の巣って見たことあるのかよ」
「つんつんおっ立って、好き勝手な方を向いてるぼさぼさ頭ってことよ。それでよく履歴書が通ったわね」
「履歴書の写真はね、五年前、正志の結婚式の時にとった写真を使った。ネクタイしてる写真はあれしかない」
「呆れた」
「床屋はもう閉まってるよ」
僕は浮き浮きと言った。「この辺、田舎だからさ、深夜営業の床屋なんかないよ。これで行くしかないね」
僕の髪は生まれつき、固く、黒く、好き勝手な方向を向いて生えている。それが僕の自然状態だ。てんでにばらばらな方向を向きたがる髪を、ドライヤーで、トニックで、ジェルでポマードでスプレーで、その他思い出したくもないありとあらゆる不愉快な手段を行使してねじ曲げ、同じ方向を向かせるのは理不尽じゃないか。個性の抹殺は時代の流れに逆行すると思う、と言う前に、聡美は部屋から消えていた。
あいつは僕の意見には絶対に賛同しないと決めている。生まれる前からだ。僕が期待してたのは子分になる弟で、役立たずの妹じゃなかった。病院で皆が、猿みたいな顔をした赤ん坊を見せて、「かわいい妹ができて良かったわね」と言った時、これは裏切りだとはっきり思った。
裏切者は、おばあちゃんの使ってた大きな裁ちばさみを持って戻ってきた。僕はぎょっとした。
「何する気?」
「そのうざったい前髪だけでも切ってあげる。それだけでも、ずいぶん違うはず」
「やめてくれ」
その時僕が感じた恐怖は、フロイト的なものじゃない。聖書のサムソンも頭になかった。もっとずっと個人的で切実な、肉体的な恐怖だ。
聡美は恐ろしくぶきっちょなんだ。
「大丈夫。痛くしないから。このハサミ、よく切れるのよ」
聡美は、カチャカチャとハサミを鳴らした。
よく切れるから怖いんじゃないか。
「いいよ。ちゃんとブロウして、ヘアスプレーでガチガチに固めていくから」
「切っといた方が、まとめやすいわよ」
「いいって」
僕はダッシュして部屋を飛び出した。廊下を駆け抜けてトイレに飛び込んでロックした。
「ちょっとー、何やってんのよ。やだー、信じられない」
聡美ののんきな声がトイレのすぐ外でする。
「冗談やめてよ」
「冗談じゃないよ。お前、本気で僕の髪、切るつもりだろ」
「その方がいいと思うからよ」
「ごめんだよ。血まみれになって、面接どころじゃなくなるよ」
「やだ、大げさね」
「チビのこと考えてみろ」
チビは、うちで飼っていた柴犬だ。信州の涼しい高原で生まれたせいか、夏の暑さに弱かった。舌を出してあえいでいるチビを見て、小学生の聡美は、毛を刈ったら、涼しくなるに違いないと考えた。ハサミを持ち出してチョキチョキとやり始め、腹のあたりをやっていて、うっかり、たくさんある乳首の一つをチョキン、と。血がどぱーっと出て、聡美は泣き叫んだ。被害者のチビの方は、あんまり騒がなかったように思う。母が獣医に連れていって、しかるべく処置してもらった。「大丈夫、わんちゃんはいっぱい、おっぱい持ってるから」獣医はまだ泣きじゃくってる聡美に言った。「でもね、ハサミをいたずらしちゃいけないよ。危ないからね」
僕は聡美に、獣医のこの言葉を思い出してもらいたかったのだ。
ドアの向こうで、しばらく沈黙が続いた。
「わかった」
不満そうな声が聞こえた。
「ハサミ、戻してこい」
「登なんか大嫌い。せっかく心配してやったのに」
僕はジェルで髪を撫でつけ、「ハードネット」を謳っているヘアスプレーで、がっちりと固めた。コンクリートなみに、浅草の「雷おこし」なみに固めた。以前、貰い物の雷おこしをかじったら、歯が欠けた。周りから、カルシウムが不足している証拠だと言われた。エンゲル係数が高いと、カルシウムが足りなくなる。貧すれば歯が欠ける。歯医者へ行く金がないから、ますます欠ける。やはり貧乏は良くない。なんとかして、正社員になろう。憧れのボーナスと退職金と厚生年金を手に入れるのだ。
周りのライバルたちの頭を見ると、真っ黒なのからごま塩っぽいのまで、グラデーションはあったが、みんな、頭にはりついたように「まとまって」いる。暗い色のスーツと同じで、これが、「社会に期待されている人材」のスタイルらしい。その点についちゃ、聡美はまちがってなかった。別に驚きはしない。聡美はいつも、正論しか言わない。
部屋の中はしんとして、空調の音がやけに耳につく。誰も何もしゃべらない。うつむいてスマホをいじったり、パンフレットらしきものをパラパラとめくったりしている。映画館や劇場の上演前とちょっと似てる。手持無沙汰でいながら、これから始まるイベントへの期待感と緊張感が漂っている。ただ、ここには、コーラもポップコーンもない。歯医者の待合室の方にもっと良く似てるかもしれない。陽気さのかけらもない、不吉なサスペンスだ。
僕は部屋の真ん中へんに、空いてる席を見つけてすわった。
隣の席には日焼けした筋肉質の男がすわっていた。机の上に、頑丈そうなアタッシュケースを置いている。男は怯えたような顔で僕を見た。
僕は安心させるようににっこりと笑って、こんにちは、と言った。
「だいぶ、待っていらっしゃるんですか」
と、話しかけると、男はますますどんぐり眼になった。
「ええ、まあ」
と、ささやくような小声だ。別に、内緒話をしているわけじゃないんだから、普通に話せばいいのに。立派な体格してるくせに、気が小さいのかな。神経衰弱になったシルベスター・スタローンみたいだ。
「どんなこと、聞かれるんですかね?」
僕が言うと、さあ、と自信なさそうに言葉を濁してうつむいた。
その時、ドアが開いて、さっきの案内係が、クリップボードを片手に入ってきた。
「お待たせいたしました。マスゾノさん、サトウさん、オノさん。お荷物をお持ちになって、こちらへおいで下さい。おあとの方は、もうしばらく、そのままお待ちください」
男二人と女一人が、ごそごそと立ち上がって出ていった。
「始まったみたいですね」
僕はもう一度、会話を試みた。
「ええ」
「なんの順番で呼んでいるんでしょうね。五十音順じゃないみたいだし、応募書類を受け付けた順番かな」
「さあ、よくわかりません」
男は言って、身体を少し斜めにして僕に背を向けるようにした。薄いパンフレットの中に鼻を突っ込むようにして一心不乱に読み始めた。内気な男らしい。
僕の前にも、会社のロゴの入ったA4サイズの封筒がある。さっきの案内係が言ってた会社案内だ。暇つぶしに、見てみることにした。
未来への展望。と表紙にある。その下に西暦と会社名とロゴ。つるつるの上等な紙で、触るのが申し訳ないようだ。パラパラとめくると、真ん中のページがぱっと開いた。センターフォールドってやつ、外国の雑誌だと若い女の子のヌードなんかが載ってるページだ。このパンフにそれはなかった。その代わりに、わっと目を引く鮮やかなマリンブルーのページが現れた。銀色の水玉が見開きページいっぱいに飛び散っている。その中に、夢、とか、希望、とか、成長、とか、実現、とかのポジティブ系の言葉が大きな活字でちりばめてある。変なの、と思った。水玉模様と夢の実現、なんの関係があるんだろ。
それ以外のページはわりとまともで、業績のグラフなんかが載ってた。一番最後のページは、年表形式の会社の歴史で、僕はそこまで見て、パンフレットを閉じ、封筒に戻した。なんか眠くなった。ふわああああとあくびをして、両腕を頭の上にあげて、うんと伸びをした。肩と首を動かして、カクカクする。視線を感じてふと見ると、隣の「神経衰弱」がまじまじとこっちを見ている。目が合うと急いでまた、パンフレットに鼻を突っ込んだ。社交的な気分になったわけじゃないらしい。仕方ない、廊下をトイレまでジョギングしてこようかと思い始めた頃、また、ドアが開いて案内係が顔を出した。クリップボードを読み上げる。
「ワタナベさん、ナガノさん、エガワさん、どうぞ」
隣の「神経衰弱」が立ち上がった。僕の方を向いて「お先に」と蚊の鳴くような小声で言った。僕が立ち上がると、ぎょっとしたような顔をした。僕も呼ばれたんだよ、また一緒だね、と僕は、愛想のいい笑顔を見せてやった。彼を元気づけてやりたかったのだ。
第二章 美女と野獣
案内係に従って、僕らはエレベーターで二階上に上がった。「僕ら」というのは、口をきっと引き結んだ、引っつめ髪の女と「神経衰弱」と僕の三人だ。今度連れていかれた部屋には、窓があった。どんよりとした曇り空とビルの間を縫って走る高速道路が見えた。窓を背にしてテーブルが据えてあって、男が二人と女が一人、すわっている。部屋の中央に、彼らと向かい合うように、パイプいすが三つ並んでいる。その前にテーブルはない。これはフェアじゃない。僕らだけ無防備に全身をさらしてすわることになるじゃないか。処刑用の電気椅子みたいだ。
三人の面接官は、机上の書類を見ながら、何か低い声で話し合っていた。案内係に促されて、僕らは電気椅子にすわった。左から、「ひっつめ」「神経衰弱」、僕の順になった。
その時、ちょっとした事故が起きた。
「神経衰弱」が、持ってたアタッシュケースを僕との間の床に置こうとして、僕の足の上に倒してしまったのだ。ズン。やつは、ウエイトトレーニング用のダンベル一そろいを持ってきたにちがいない。僕の左足の甲に、十トンはある重さがのしかかった。僕は思わず「うわっ」と声を上げて立ち上がり、この間抜け野郎! と怒鳴りつけようとした。「神経衰弱」は例によって小さな声で謝罪の言葉をつぶやきながら、十トンアタッシュを引き起こした。その手が細かく震えているのを見て、僕の怒りは萎えた。気の毒に、緊張しきっている。
騒ぎが収まってから、「それでは、面接を始めさせていただきます」と、向かって右側の男が言った。
この男は、四角い顔にコッカースパニエルのようなうるんだ悲し気な目をしてる。これでちょびひげがあって、バラの花を一輪持たせれば、チャップリンだ。チャップリンはロンドンの最下層の貧困家庭からはい上がった。彼の演じる浮浪者には、人生の悲哀と、それを笑い飛ばす活力の両方が感じられる。僕が彼の映画が好きな理由だ。もっとも、このチャップリンは、映画の浮浪者よりだいぶいいスーツを着ている。
左側に座っているのは、面長で色白で、親近感を抱かせる美人だ。メリル・ストリープに似てる。僕の好みのタイプ。さっき、「神経衰弱」が十トンアタッシュで僕の左足を粉砕しそうになった時、椅子から立ち上がって、「大丈夫ですか?」と心配そうに尋ねてくれた。美人なだけじゃない、思いやりのあるひとなんだ。淡い桜色のパンツスーツがとても良く似合ってる。
中央に座ってる男は中肉中背のどこといって特徴のない、目立たない男だ。真ん中にすわってるんだから、こいつが一番偉いんだろう。聡美の言っていたとおり、目立たない男は出世するらしい。
「ありがとうございました。では、次、江川さん」
名前を呼ばれてはっとした。三人の面接官を観察している間に、「ひっつめ」と「神経衰弱」はひとしきり、何かしゃべったらしい。僕は何を言えばいいんだろ。「あの、質問をもう一度」って言ったら、僕が何も聞いてなかったことがばれちゃうな。いかになんでもそれはマズイだろう。
僕は冷や汗をかいた。江川登、絶体絶命の危機。手のひらにじっとりと汗がわき出てきた。額にも汗がにじみ出てくる。僕はズボンのポケットからハンカチを出して汗をふいた。正面の三人はじっと僕を見つめている。僕が何か言うのを待っている。一秒の何分の一か、彼らの背後にある窓を指さして、「あ! UFO!」と叫ぶ誘惑にとらわれた。もちろん、それはしなかった。そんなことするくらいなら、立ち上がり、よろよろと三歩歩いてから、左胸を押さえて、ばったりと倒れた方がましだ。UFO出現より、突然の心臓発作の方が、観客のビリーバビリティは高い。
僕は覚悟を決めた。立ち上がった。ふらりとよろけた。おっとっと。そして、足元にあった「神経衰弱」の十トンアタッシュを思いきりけとばした。
アタッシュケースは床の上を弾丸のようにすっとんでいった。その先には、「目立たない男」が腕組みしてすわっている。僕らはみんな、声なき悲鳴をあげた。「神経衰弱」は、実際に、「ああっ」と悲痛な声をあげた。ところが、「目立たない男」は意外な反応をした。自分に向かってすっ飛んでくるアタッシュケースをきっと睨み、足元に飛んできたそれをぴたり、と右足で止めた。ナイス! 拍手喝采こそしなかったが、惚れ惚れするようなガードぶりだった。
「失礼しました」
僕は丁重に謝罪し、「神経衰弱」はすみません、すみませんと呪文のように唱えながら、アタッシュケースをテーブルの下から回収した。メリル・ストリープは「神経衰弱」がアタッシュケースを再び足元に置こうとするのを見て、「それ、離れた所に置いた方がいいのじゃないですか」と、建設的な発言をした。彼女は出世するだろう。今は、「目立たない男」の後塵を拝していても、きっと、いつか、この会社のCEOにまで昇りつめるに違いない。そして、副社長は僕、となればしめたものだが、それにはまず、正社員になる必要がある。
「神経衰弱」は、ちらりと僕を見て、何も言わずに十トンアタッシュを、部屋の一番後ろの壁際に置いた。名ゴールキーパーの片りんを見せた(まったく、ひとは見かけによらない)「目立たない男」は一言も言わない。ワイシャツの袖をめくるようにして時計を見た。
「ええと、どこまでいきましたっけ」
チャップリンが困ったように言って、机の上のメモを見た。「そうでした。江川登さん。自己紹介をお願いします」
「かしこまりました」と僕は言って、えへん、と咳払いをした。チャップリンは、時計を睨んでいる「目立たない男」の方を見て、「予定が押していますので、なるべく簡潔にお願いします」と言った。僕は、心配いらない、というように、チャップリンに向かって軽くうなずいてみせた。
自己紹介については、僕はエキスパートを自負している。役者だからだ。うちの演出兼座付作家の後藤はいつも言う。
「舞台に登場したその瞬間が勝負だ。役者は一瞬で、自分を観客の目と耳に印象づけなければならない」
僕は反論した。
「それはセリフ次第だよ。おはよう、とかじゃ誰も気にとめないよ」
後藤は冷たい目で僕を見た。
「お前って、どこかの国の万年野党に似てるな。反論専門」
「いいセリフが欲しいって言ってるだけだよ。生きるべきか死ぬべきか、みたいな」
「うるさい。それなら自分で書きゃいいだろ」
怠惰な座付作家を持つと、役者は苦労する。もっと苦労なのは、観客が注意深く、舞台やスクリーンに注目してるなんて全然期待できないことだ。観客の心は大概、他のもっと重要な案件に占められている。この椅子は座り心地が悪いとか、前の客の禿げ頭が目障りだが、席を移ることはできるだろうかとか、隣の彼女がさりげなく肘掛けに手をおいたが、これは手を握ってもいいという合図だろうかとか、後ろのガキが僕の背中を蹴とばすのを止めさせるように、親に文句言ったらやっかいなことになるだろうか、とか、後藤のやつ、いつまでポップコーンを抱え込んでるんだ、そろそろこっちに回せ、半分は僕の権利なんだぞ、とか、色々心配ごとで気が散ってるものなのだ。それに比べりゃ、面接官が注意深くこっちの話を聞いてくれる面接なんてお茶の子だ、と僕は思う。
だが。
聡美は僕の自己紹介をけちょんけちょんにけなした。
「あんた、馬鹿」
昨夜、僕のドレス・リハーサルを見た聡美は言った。「就職面接はオーディションじゃないんだって、何度言えばわかるのよ」
「同じだよ。たくさんいる候補から、一人を選ぶんだから」
「目的が違うでしょうが。彼らが求めているのは、常識を備えた、真面目な、組織の中でうまくやっていける、一人前の社会人なのよ。狂人の振りして廊下をうろつくマザコンの王子も、すかした減らず口たたく私立探偵もお呼びじゃないの」
「ハムレットはマザコンじゃないと僕は思ってる。むしろファザコンで……」
「ハムレットは忘れなさい!」
聡美は金切り声を張り上げた。「あんたは明日、まともな社会人の自己紹介をするの。正社員になりたくないの?」
「なりたい」
それから僕らは、聡美の言う、「無難で好感の持てる自己紹介」を稽古した。気の抜けたセリフの連続だが、それが台本ならしょうがない。僕はプロだ。超極上の面接受けする社会人Aを演じてやる。一時間ばかり、聡美のダメ出しを受けながらリハーサルを繰り返し、ようやくOKが出た自己紹介の本番だ。
第三章 ショウほど素敵な商売はない

僕は立ち上がり、背筋を伸ばした。三人の面接官を順々に見てから、中央の「目立たない男」に視線を据えて、「江川登です。よろしくお願いします」と朗々と発声した。男がうなずいて、「すわりたまえ」と言った。初めて「目立たない男」の声を聞いた。いいぞ。股旅ものだったら、「さっそくお控えいただき、ありがとさんにござんす」ってとこだ。僕は腰をおろし、聡美のご指導通りの自己紹介を始めた。「 」が聡美ヴァージョン、( )は、ボツになった僕ヴァージョンだ。
「まず、このように面接の機会をいただけたことを感謝いたします」(問われて名乗るもおこがましいが)
「出身は、東京都です」(江戸は御府内、朱引きのうちの都営団地、2LDKで産湯をつかい)
「幼い頃からテレビのドラマが好きで、中学、高校は演劇部に入りました」(ガキの折りより身状が悪く、学問嫌れえな道楽息子)
「高校の演劇部では、老人ホームや障碍者施設の慰問活動に励みました」(関八州を流れわたり、遊びはすれど非道はせず、人に情けをかけたまち)
「大学は文学部に進み、主にフィールドワークを中心にして古代史を学びました」(普段着慣れしTシャツジーンズ、旅を小股に西国をまわりまわって邪馬台国)
「卒業後は小劇団に属し、アルバイトをしながら演劇活動を続けてきました」(打ち込む芝居も身の破れ、もはや三十路に気が付けば、平均寿命は八十余幾歳)
「それなりの成果はあったと思います。しかし、両親も年を取り、私のことを心配しています。私自身も、きちんとした仕事につきたいと思うようになりました。自分の今までの経験から、人との関わり、コミュニケーション能力には自信があります。御社のお役に立てると思い、応募いたしました」(どうで終めえは野垂死、覚悟はかねてシベリア候、孝行の道も知らぬに多摩プラザ、夢を果たせしマイホーム、段々坂々登れぬ父母、年には勝てぬ世の無情、哀れ悲しやなさけなや、思い知らされ罪業に、頼ってみたが御社の求人、柏手打ったが運の尽き、ご先祖激怒の面接通知、古いかばんのちり払い、張り付き頭で駆けつけた、その名もお役者、江川登)
僕は一礼した。うまくやったと思う。聡美の作った「自己紹介」は面白くないが、わかりやすいのが取り柄だ。
三人は時折、メモを取りながら聞いていた。チャップリンと「目立たない男」は終始無表情だったが、メリル・ストリープは、終わった時、力づけるような笑顔を見せてくれた。いいぞ。僕は彼女が大好きになった。結婚してるのかな、彼女。
チャップリンは「ありがとうございました」と僕に言うと、再びメモを見た。「次の質問ですが、なぜ、わが社の募集に応募されたのか、理由をお聞かせ願います。渡辺さん」
「ひっつめ」がぴくりと動いた。一本の乱れもなく後ろにひっつめた髪を、さらに撫でつけた。心理学者によれば、自分の身体や頭を意味もなくいじるのは、緊張している証拠だ。そうやってリラックスし、自信を取り戻そうとする。僕は横目でじっくりと「ひっつめ」を観察した。三十歳くらいかな、僕よりちょっと若いかもしれない。濃紺のスーツ、白いブラウス、スカートは膝丈、肌色のストッキングに中ヒールのパンプス、控えめの化粧。無個性なとこが好感度満点の面接ファッションだ。聡美は満点花丸をつけるだろう。中型のバッグを小脇に抱えると、いかにも有能、優秀、キャリアウーマンだ。でも、髪を撫でつけるとこみると、やはり緊張してるんだ。どういう人なんだろう、と僕は興味を持った。さっき、ちゃんと自己紹介を聞いておけばよかった。
「ひっつめ」は、会社の将来性に賭ける、というようなことを熱心にしゃべった。二十一世紀は、人々が健康を特に気にかける時代になるそうで、健康食品やサプルメントを扱うこの会社の未来は、大いに明るいのだそうだ。この会社の主力商品は「マリーン・ナーチャー」なる清涼飲料で、これが大ヒットして急激に業績を伸ばした。「マリーン・ナーチャー」は海水から何とかいう成分を抽出したものが基になってる。海はそもそも、地球生物全ての故郷だから、「マリーン・ナーチャー」は身体にとてもいい効果をもたらすんだそうだ。「海のお宝、マリーン・ナーチャー、一本飲んだら、毎日元気、ハッピー、ヤッホー、オーケードーケー、チャンチャンチャンX2」というテレビCMは僕も知ってる。「ひっつめ」の話を聞いているうちに、僕の気持ちも明るくなった。そんなにすごい製品を作っている会社の正社員になれたら、きっと一生安泰だぞ。ちっとぐらい残業があったって、社員割引でマリーン・ナーチャーを安く手にいれて毎日飲めば、定年まで元気に勤められるだろう。退職金もらってリタイアした後も、OB割引制度があるだろう。いいことづくめじゃないか。なんとしても、この会社に潜り込むんだ、と僕は決意を新たにした。
「ひっつめ」がしゃべり終わった。
「ありがとうございました。次、長野さん」
チャップリンの言葉で、「神経衰弱」が何か言った。小さな声でぼそぼそ言うものだから、よく聞こえない。隣にいる僕に聞こえないんだから、面接官には当然聞こえない。すぐにチャップリンが、「長野さん、もう少し大きな声でお話しください」と言った。メリル・ストリープが力づけるような笑顔を見せて、「ゆっくり、落ち着いて話してくださいね」と言った。彼女は求職者の守護天使だ。優しい言葉に、「神経衰弱」は自分を取り戻したらしい。ボリュームを1から6ぐらいに上げて、志望理由を話し始めた。驚くべき話だった。「神経衰弱」はマリーン・ナーチャーに一命を救われたのだ。
大学卒業後、新卒で入った会社で上司と合わず、パワハラを受けて、心に傷を、胃に潰瘍を患った。私生活でもトラブルが続き、毎日が陰鬱で暗かった。誰に相談することもできず、こうなったのは身の不徳のいたすところと自己責任に苦しみ、自虐のリンボに落ち込み、この苦痛から逃れるには、この世におさらばするしかないと思いつめた。屋上と踏切がひたすら魅力的に見えていたその頃、ふと、テレビでマリーン・ナーチャーのCMを見た。その陽気な能天気に、「神経衰弱」は反感を持った。俺がこんなに苦しんでいるのに、何がチャンチャンチャンだ。「CMなんてどうせ嘘八百、大衆から金を搾り取るために広告会社の作ったおとぎ話だ、甘い罠だ、毒だ、効くはずがあるもんか、馬鹿にしやがって」と、「神経衰弱」氏は震える声で言った。背中を押された気持ちになった。よし、飛び降りも飛び込みもやめだ。どうせ死ぬならこいつを飲んでやる、中毒死してやる、と無情な世の中に復讐するつもりでぐっとマリーン・ナーチャーをあおった。獄中のソクラテスもかくや。「神経衰弱」、かっこいいじゃないか。すると、奇跡が起きた。マリーン・ナーチャーが喉を通り、食道を下っていくうちに、やる気がふつふつと湧いてきたのだ。火山地下のマグマが不気味に胎動するように、元気と勇気が地表に向かってぐんぐんとせりあがってきた。「神経衰弱」氏は思わず、「ああーっ」とため息をついた。その日以来、マリーン・ナーチャーを愛飲している。夜、よく眠れるようになり、朝の目覚めが爽やかになった。彼岸への引っ越し願望はきれいに消えてしまった。
「ハローワークで御社の求人を見つけた時は、これぞ天啓と思いました。この会社に就職し、マリーン・ナーチャーの素晴らしさを全世界の人類に知らしめたいと、応募した次第であります」と、「神経衰弱」は締めくくった。
なんというドラマだ。なんという壮大な抱負だ。ほとんど新興宗教のノリじゃないか。だが、感動的な内容のわりに、効果の方はいまいちだった。「神経衰弱」氏の真剣には疑いがない。膝に握りこぶしを置き、必死にしゃべっている。だが、無表情な一本調子でぼそぼそやられては、魂の叫びも掛け算の九九と同じ効果しか与えない。さらに、声が小さい。天地を揺るがす大音声でやれとは言わないが、慎ましい声にも限度がある。「神経衰弱」の声はボリューム6から徐々に降下し、終わりの方は0・5くらいにまで下がっていた。それにつれて三人の面接官の表情も段々険しくなり、額にしわを寄せ、テーブルの上に身を乗り出すようにして一心に耳を傾けていた。TOEICのリスニング試験を受けてる受験生だって、あそこまで必死に聞き取ろうとはしていない。「神経衰弱」の話が終わると、誰ともなくため息が漏れ、部屋全体に弛緩した空気が漂った。「神経衰弱」は全力を使い果たしたように、ぐったりと首を垂れ、爪先を見つめている。マリーン・ナーチャーの効力も、この程度じゃあやしいもんだ。この会社の未来は、それほど明るいものじゃないかもしれないぞ、と僕は不安になった。
「ええ、では次。皆様のセールスポイントを」と、チャップリンが気を取り直して言い始めると、「待って」とメリル・ストリープがさえぎった。「もう、おひとかた、いらっしゃるでしょう。江川さんの志望動機をまだ、うかがってません」
チャップリンは、はっとしたように僕を見た。「ああ、そうでした。失礼しました」テーブルの上のティッシュでやたらと顔をぬぐった。「では、江川さん。我が社に応募された動機をお聞かせください」
正直言うと、僕はとばしてもらっても良かったんだ。チャップリンがへまをやった時、内心、しめた、と思った。でも、やっぱり、言わないわけにはいかないらしい。
「志望動機って、そりゃ、決まってるでしょう。正社員になるためですよ。今のご時世、『正社員の中途採用』なんてあまりありませんからね。ハローワークで御社の求人を見た時に、とびつきましたよ。株式会社『ネクスト企画』なんて知名度の低い、それもとびきりインチキくさい名前の中小企業だからってかまやしません。週休二日で、九時五時勤務で、年休百二十五日、年収三百万円以上で、年二回賞与があって、退職金があって、社会保険完備のホワイトカラー職だったら、試してみる価値は十分ありますよ。僕は、定期航路船から後先考えずに飛び降りた口でしてね、浮世の水の冷たさ塩辛さは、たっぷりと味わいました。このまま誰にも知られずに、むなしく水底に沈むのか、と半ばあきらめていたところに、なんと、船が近づいてくるじゃあありませんか。もちろん、御社のことですよ。水平線の彼方に消えていった大型クルーズ船と比べると、いささか頼りないポンポン蒸気ですがね、贅沢は言ってられません。狸の泥船でなきゃ御の字だと、大声をあげて呼んだら、なんと、ロープを投げてくださった。地獄に仏、極楽の蜘蛛の糸とはこのことだ。今、しっかりと握りしめ、せっせと登っております。よろしゅう、御頼み申します」
こうしゃべったら、僕は正真正銘の馬鹿だ。いつも誠実を心がけてるが、そこまで馬鹿正直じゃない。聡美が作ってくれた志望動機を暗記してきたよ。御社に就職し、人様の健康に役立つ仕事をしたい云々ってやつだ。優等生的な、面白味のない僕の志望動機を、三人の面接官は、にこりともしないで聞いていた。僕は不安になった。
観客の反応に、いちいち左右されちゃならないのは、百も承知してるが、役者だって人の子、憎まれるより愛されたいんだ。シェイクスピアだと、悪役にも花があって、イヤゴーみたいにその悪漢ぶりがかえって観客に気に入られるものなんだけど、ギリシア悲劇はそうはいかない。「メディア」のイアソンなんて悲惨だった。恩知らずの勝手な男で、おまけに浮気な夫の代名詞みたいな役だ。観客はたいてい、男より女が多いから、下手すると劇場の七割の人間を敵に回すことになる。一言台詞を言うたびに、ライトの向こうの暗い観客席から無言の憎悪の視線を浴びせられて、僕は毎晩へとへとになった。トラウマだ。僕は愛されたい。社会人Aは人気がない。これは何とかしなきゃいけないと、僕は決心した。
「ええと、では、最後に、皆さんのセールスポイントを一言でお聞かせください。渡辺さん」
チャップリンの言葉に、「ひっつめ」は、積極性です、と答えた。なんでも積極的に、前向きに考える性格なんだそうだ。そして、「神経衰弱」は、なんと、コミュニケーション能力だと言った。人がいかに自分をわかっていないか、良い例だろう。
「次、江川さん。時間が押しているので、一言でお願いします」
チャップリンの言葉に、僕は胸を張って、「想像力です」と答えた。「想像力はすべての基本です。僕は御社に入社した後の、自分の仕事ぶりを想像することができます」
「ほう」と、「目立たない男」が興味を持ったように身を乗り出した。「どのように?」
短くしろと言ったじゃないか、と僕はチャップリンの方を見たが、奴はあさっての方を向いている。仕方なく、僕は続けた。
「まず、マリーン・ナーチャーの売り上げを倍増させるという目標を掲げます」
「大きな目標だな」
と、「目立たない男」が言った。どことなく嘲笑の響きがあるのが、気に入らない。
「目標は大きい方がいいのです。倍増じゃ足りない。そうですね、三百パーセントアップとしましょう」
メリル・ストリープが目を輝かせて僕を見ている。僕は嬉しくなった。
「それから、この売上アップ計画のためのプロジェクトチームを社内に立ち上げます」
「プロジェクトチームねえ」
「目立たない男」は嫌味たっぷりに言った。「で、プロジェクトリーダーは君かね?」
「もちろんです」
「随分、自信があるんだな」
「目立たない男」は嫌な笑い方をして、チャップリンの方を見た。面接はそこで終わり、僕らは退出した。「神経衰弱」は、十トンアタッシュを忘れそうになり、メリル・ストリープに注意されてあわてて取りに戻った。部屋から出る前に視線を感じて振り返ると、メリル・ストリープが他の二人と離れて、一人、こっちを見ていた。なぜか、不安そうな表情に見えたのは、僕の気のせいだろうか。
第四章 雨に唄えば

外は雨が降っていた。
そう言えば、今朝の天気予報で雨が降ると言っていた。太平洋高気圧の力がいまいちで、梅雨前線はまだぐずぐずと東海地方に居座っている。「ひっつめ」は、かばんから折りたたみ傘を出すと、「お先に」と言って、さっさと出ていった。僕は傘を持ってない。空を見上げると、意外に明るい。小降りになるのを待とうと、ロビーにあった椅子に腰をおろした。「神経衰弱」は、空を見たり、僕の方を見たりしてもじもじしている。彼も傘を持ってないんだろう。「すぐに止みますよ、にわか雨だ」と、僕が言うと、はあ、と要領を得ない返事をする。そこで突っ立ってられるのも落ち着かないので、隣の椅子を叩いて、「掛けませんか」と誘ってみた。はあ、とはっきりしない返事。こいつが年取ったら、電車で席を譲られても、何かはっきりしない理由ですわらなくて、勇気を出して席を譲った小学生に惨めな思いをさせるにちがいない。満員の電車の中、歯が抜けたようにポツンと一人分だけ、席が空いている。周りの大人は知らんふり。空席の傍で赤い顔して唇をかみしめている子供を思い浮かべて、僕は義憤に駆られた。「すわったらいいでしょう、空いてるんだから」僕が強く勧めると、「神経衰弱」はびっくりしたような顔をした。「おすわりなさい!」僕は隣の椅子をポンポンと叩いた。「神経衰弱」はすわった。
雨は降り続いている。
薄暗いロビーには人けがない。湿った空気の中に、かすかに百合の花の香が漂っている。U字型の立派な受付デスクに、鉄砲百合とピンクのカーネーションを生けた大きなガラスの花瓶が置いてあるが、誰もいない。鉄砲百合もカーネーションも好きな花だが、できるだけ雨に濡れずに地下鉄の駅まで行く方法を教えてはくれない。合理化も結構だが、人間にしかできないこともある。
雨は降り続いている。
エレベーターが下りてきて、また三人の求職者が出てきた。僕らの方をちらと見ると、折り畳み傘をさして出ていった。
「神経衰弱」は、僕に背を向けるようにして、ガラス扉の向こうで水しぶきをあげて走る車を眺めている。十トンアタッシュは膝に載せている。これといった特徴のない黒いアタッシュケースだ。僕はあの、足の甲にずしりとのしかかった重みを思い出した。何が入っているのだろう。映画だと、こういうアタッシュケースには、誘拐犯から請求された身代金か密輸されたヘロインの代金を入れることになっている。帯封のついた福沢諭吉がずらっと並んでいるところを想像した。エキサイティングだ。隣席の男の顔をうかがった。「神経衰弱」は、しょんぼりと肩を落としてすわっている。大金を抱えている男には見えない。何が入ってるんだろう。ヒトラーを暗殺しようとしたドイツ国防軍の将軍たちが作戦指令室に持ち込んだ爆弾は、こういうアタッシュケースに入っていた。耳を澄ましてみろ。カチカチという時計の音が聞こえないか?
時計の音は聞こえなかったが、代わりにエレベーターの到着を知らせる電子音が響いた。ドアが開いて、さっきの案内係と、三人の求職者が出てきた。最後の回の面接が終わったのだ。案内係は、椅子に座っている僕らを見て、変な顔をした。
「ここで何をしているんですか?」
雨宿りです、と言うと、ガラス扉の方を見た。雨はさっきより激しくなっているようだ。案内係は、ああ、と納得したように言ってエレベーターに戻っていった。三人の求職者は次々に折り畳み傘を取り出して出ていく。気象庁ではなく、自分の勘と運を信じたのは、僕と「神経衰弱」の二人だけらしい。急に「神経衰弱」に親しみがわいた。「おお、同志よ」と肩をたたいてやりたくなった。
「ワタナベさん」と声をかけた。反応なし。「神経衰弱」はそっぽを向いたまま、強まる雨脚を眺めている。僕は声を張り上げた。「ワタナベさん!」同時に、つんつんと、人差し指で彼の肩をつついた。「神経衰弱」は一メートルほど飛び上がった。まるで僕が、人差し指じゃなく、魔女裁判で使われた太い針を突き刺したかのような顔で振り向いた。
「僕ですか?」
「あなたです」
他に誰もいないだろうに。
「僕はワタナベじゃないです。長野です。長野県の長野です」
憤慨したように言う。「ワタナベっていうのは、さっき帰っていった女性の方ですよ。僕は長野です。長野県の長野」
そうか。なに、大したことじゃない。わかればいいのだ。
「それじゃ、長野さん。僕は江川登といいます」
「知ってますよ」
と、不機嫌そうに言う。「江川又助の一族の方でしょう?」
僕はたいていのことには驚かない。舞台というのは、突拍子もないことが、あってはならないことが度々起こる、世界で一番呪われた場所なのだ。僕は一度、泣いてる姫君にハンカチを差し出したつもりが、短刀を突き付けるはめになったことがある。快晴の五月のピクニックに出かけたはずが、一瞬にして暗闇になったこともある。あの時は、あろうことか、月まで出た。それでも芝居は続けなければならない。世界が崩れ落ちようとも、芝居は続く。役者が生けっ太いのは、長年、この不条理な世界をアトラスのように双肩に支えてきたからにほかならない。だが、この時ばかりは僕はわけがわからず、黙っていた。「神経衰弱」は重ねていった。
「そうなんでしょう? 名前を聞いた時にピンときたんです」
僕は一向にピンとこなかった。
「江川又助って誰だ?」
「また、そんな。しらばっくれたって駄目ですよ」
この会社の創業者ですよ、と「神経衰弱」は言った。彼の説明によると、ワンマン社長で有名だったが、去年CEOを退いて会長になった。でも依然として権力を握ってる、よくあるタイプの食えないじじいらしい。
「江川又助はあなたの大叔父さんですか? もしかして、祖父とかですか?」
「知らないよ。僕の親戚に、又助なんてアナクロな名前の奴はいない」
「隠さなくていいですよ」
「隠してない! 本当にいないんだ」
「また、そんな。あなた、控室でも面接でもすごくリラックスしてた。江川又助の孫だからでしょう? 落とされるわけないですものね」
これは聞き捨てならない。僕がここにいるのは、かしわ手のたたりと、聡美の特訓と、ガチガチに固めた貼り付き頭を作り上げた僕の努力の成果だ。縁故入社を疑われるのは心外だ。僕はその事情をるる説明したが、「神経衰弱」は全く取り合おうとしなかった。
「江川又助の孫だったら、上の方に顔がききますよね。おじいさまに、採用枠をもう一人、増やしてもらえるように頼んでくれませんか」
僕はすっかり、前CEOの孫ということになっていた。
「僕は本当に、この会社のために、生涯かけて働くつもりなんです。なんていっても、僕が今生きてるのは、マリーン・ナーチャーのおかげなんですから」
奴は十トンアタッシュを開けた。中には、ぎっしりと、マリンブルーに銀色の水玉模様のアルミ缶が詰まっていた。マリーン・ナーチャーはツーコインで買えるほど安くはない。これだけ並ぶと壮観だ。「神経衰弱」は一つ取り上げてプルトップを引き抜いた。ごくごくと一気に半分くらいを飲み干す。見る見るうちに表情が変わった。どんよりと濁っていた暗い眼差しに星の光がさした。日焼けした頬がうっすらとバラ色に変わり、口元に深い笑い皺が刻まれ、鼻と口からふぉふぉふぉと妙な音が漏れてきた。「神経衰弱」は笑っているのだ。彼は、ぱ、と立ち上がるなり、身振り手振りを交えて歌い出した。
♪ 海のお宝、マリーン・ナーチャー、
一本飲んだら、毎日元気、
ハッピー、ヤッホー、オーケードーケー、
チャンチャンチャン、それ、チャンチャンチャン
僕は阿呆みたいに呆然と眺めていた。
就職面接会場の薄暗いロビーで、フレッド・アステアよろしく歌い踊る「神経衰弱」。
今までに見たどんな前衛演劇よりも不気味でシュールな光景だった。
「神経衰弱」は歌い納めて、くるりとピルエットを決めると、僕の隣の椅子に腰をおろした。残り半分を一息に飲み干して、「ああー」とため息をついた。目を閉じて、じっと味わうふうだ。通人の風格がある。僕は恐る恐る尋ねた。
「うまいのか?」
「生き返りますよ」
「神経衰弱」は缶を一つ取り上げて僕に差し出した。「どうぞ」
僕はあわてて辞退した。僕はマリーン・ナーチャーを飲んだことがない。能書き通り健康に良くても、確実に懐具合を悪くするからだ。飲まなくて良かった。懐よりも脳に悪影響を及ぼしそうだ。
神経衰弱は二本目を飲んでいる。
「いつもそんなにたくさん持ち歩いてるのか?」
「まさか。普段はせいぜい二本です。足りなかったら、スーパーでもコンビニでも買えますから。今日は特別です。面接の時に、これを見せて、僕がマリーン・ナーチャーの大ファンであることを力説するつもりでした。でも、あなたの名前を聞いたら、いっぺんで気が抜けました。江川又助のお孫さんと争っても、勝てる見込みはありませんから」
「だから、僕は違うって。苗字が同じなのは偶然だよ」
だいたい、江川なんてごくありふれた名前じゃないか、と僕が反論していると、エレベーターが到着した電子音がロビーに響いた。ドアが開いて、メリル・ストリープが出てきた。
「今井さんから、あなた方がここにいると聞いたものですから」と言って、ビニール傘を差しだした。
「私の置き傘なんです。いつも傘を忘れて新しく買うものだから、溜まってしまって。たくさんあるから、返さなくて結構です」
僕は感激して受け取った。やっぱりメリル・ストリープは違う。思いやりってものを知ってる。「神経衰弱」もそう思うだろうと横を見たら、奴は何か意味不明の言葉をつぶやきながら、十トンアタッシュの底をかき回してる。中から、折り畳み傘が出てきた。ちゃんと持ってるじゃないか、このインチキ野郎。僕の冷たい視線を浴びて、奴はへどもどしながら、「それじゃ」とかなんとか言うと、雨の中へ出ていった。
僕とメリル・ストリープは、暗いロビーに二人、残された。メリル・ストリープは、ちらりと左手首にはめた時計を見た。実用一点張りのデジタル時計なんかじゃない。ちょっとクラシックな、でも、上品で華奢な金色のアナログ時計で、一九三〇年代の貴婦人の持ち物といっても通りそうだった。彼女の雰囲気にぴったりだ。
「ちょうどお昼ですね」
と、メリル・ストリープは言った。「江川さん、二十分ほどお時間いただけるかしら?」
「もちろん」
って、僕は叫んだ。二十分どころか、二十時間でも二十日でも。あなたのおそばにいられるなら、二百年だって、かまいやしませんって気分だった。メリル・ストリープは微笑した。
「すぐそこにカフェがあります」
雨は降り続いている。
傘は二本あったから、残念ながら、相合傘にはならなかった。「神経衰弱」め、なんて無粋な奴なんだ。僕は今頃、地下鉄に乗っているだろう「神経衰弱」を呪った。やつの十トンアタッシュが、網棚からやつの間抜けな貼り付き頭の上に落下することを、心の底から願った。
地下鉄の駅からすぐのところにチェーン店のカフェがあった。カウンターで、僕が、と申し出たが、彼女は首を振った。「私がお誘いしたんです。何になさる?」彼女とランチなんて最高だけど、欲張り過ぎちゃいけないよな。僕はコーヒーを頼んだ。隅の方に、二人掛けの空いたテーブルを見つけた。彼女はコーヒーが二つ載ったトレイを持って、すぐにやってきた。
雨は降り続いている。
暗い雨の日は気分が滅入るが、雨の日ならではの楽しみもある。一つは、熱いコーヒーだ。どういうわけか、肌寒い雨の日に飲むコーヒーは、五月晴れの日よりも香り高く、おいしく感じられる。世の中、悪いことばかりじゃないと感じさせる。世界と和解したい気持ちになり、人生への信頼がよみがえる。テーブルを挟んで向かい側に、絶世の美女が微笑んでいる時は特に。
メリル・ストリープは、親指と人差し指で軽くカップをつまみ、慎ましくコーヒーを飲んでいる。薬指に結婚指輪ははまっていない。もっとも、これはあてにならない。日本の既婚女性で、指輪をしてないのは大勢いる。
コトン、と軽い音をさせて、彼女はカップを受け皿に置いた。
「江川さん」
澄んだ瞳で僕を見つめる。僕はもう卒倒しそうだ。心臓がパクパクいって、血管の中をどきん、どきんと血が流れる。はい、と僕はかすれた声で返事した。
「会長はプロジェクトについて、あなたに何とおっしゃったの?」
はあ?
頭の中が真っ白になった。彼女の言葉の意味がつかめない。「カイチョーハ、プロジェクトニツイテ、アナタニ、ナントオッシャッタノ?」
「あの、よくわからないのですが」
彼女は苛立たし気な身振りをした。
「江川会長は、ルネサンス・プロジェクトについて、あなたに何か指示をされたんでしょう?」
突然に理解した。彼女もだ。彼女も、僕を江川マタゾウの親戚だと思い込んでいる! 僕は、夢中で顔の前で手を振った。違う、違うのです。誤解なんです、と。
「何が誤解なの? あなたは大野部長に聞かれて、プロジェクトの話をしたじゃないの。会長からお聞きにならなかった? 大野部長は、このプロジェクトに良い感じを持ってないのよ。少々、軽率だったと思わない?」
僕は必死で、違う違うと繰り返した。
「僕は、江川会長の孫じゃないんです!」
ようやく、まともにしゃべれるようになった。「僕は会長とは何の関係もない。ハローワークで求人情報を見て、応募しただけです。名前が同じなのは偶然なんです!」
僕は一生のうちで、あれほど驚いた顔をした人を見たことがない。まさに、茫然自失、驚天動地といった表現がぴったりの表情だった。心不全起こすんじゃないかと心配になったくらいだ。
「でも、あなた、プロジェクトのこと話してた」
「あれはアドリブです」
「アドリブ?」
「何か言わなきゃいけないと思ったから、言っただけです」
「口から出まかせってこと?」
メリル・ストリープは、情けなさそうに言って、両手で顔を覆ってしまった。僕は申し訳なくて、身の置き所がなかった。この世から消えてしまいたいと、本気で思った。
「すみません」
「いえ」
メリル・ストリープは、ハンカチを出して、目のあたりを押さえた。
「ごめんなさい。私、思い違いをしてた」
「いえ。僕こそ、すみません。まぎらわしい名前で」
僕が言うと、彼女は気丈に微笑んでみせた。その後、僕らは差しさわりのない世間話をした。メリル・ストリープは、映画が好きだと言う。最近忙しくてなかなか行けないが、以前は弟と一緒に良く見に行ったと言う。シリアスなドラマよりも、軽快なコメディが好きらしい。会話の中に「うちのひと」とか、「彼氏」という言葉が出なかったので、僕はハッピーだった。彼女は僕と同じ、自由の身と知れた。マンションで一人暮らしらしい。
カフェを出る時、雨はまだ降り続いていた。しゃくだけど、気象庁の勝ちだ。彼女が持ってきたビニール傘のうち、一本は骨が二本、くにゃりと曲がってた。メリル・ストリープは僕に、曲がってない方の傘を持っていけ、と言った。優しい人なんだ。僕はきれいな傘を持って地下鉄へ、彼女は曲がった傘をさして会社へ戻っていった。
「オール・シングス・ナイス」お楽しみいただけたでしょうか?
この続きは、電子書籍(キンドル本)または、ペーパーバックでお読みになれます。
電子書籍の注文はこちらから・・・・・http://www.amazon.co.jp/dp/B0CL3ZGD2B
ペーパーバックの注文はこちらから・・・・・http://www/amazon.co.jp/dp/B0CL2ZJZ7M
このページの先頭へ戻るには・・・![]()